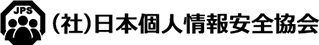新着情報
なぜ情報漏えい防止の話が社員の腹に落ちないのか 〜中間層へのアプローチが鍵〜
2025.04.16
情報漏えい防止策について解説するコンサルタントや社内研修では、対策の実効性を評価する際に、「やった」「やっていない」の2つのグループに分けることがよくあります。
しかし、現場の実情を見てみると、「時々やらないことがある」「時間があればやる」といった、“3つ目のグループ”とも言える中間層が存在し、実際には全体の9割を占めているのです。それにもかかわらず、この中間層を考慮に入れず、「やった/やらなかった」という二項対立だけで研修を進めてしまう結果、社員の納得感が得られなくなります。
私たちの多くは、「ルールを守るべきことは分かっている」「ふだんはちゃんとやっている」と思っています。でも、忙しいとき、疲れているとき、時間がないとき、つい後回しにしてしまう。こころあたりはありませんか?
情報漏えい防止対策においても、「基本的にはやっているけど、時々やらないこともある」という“層”が、全体の8〜9割を占めているとも言われ、また漏えい事故をおこした人の大半が中間層に属しているともいわれています。
そこで、「分かっているけれど、できないときもある」人に向けて、行動を変えていくための4つのヒントをお伝えします。
「これは自分のことだ」と思えるケースに触れる
事件や極端な違反例だけを聞いても、「自分とは別の話」に感じてしまいがちです。「つい確認を怠った」「忙しさに紛れて後回しにした」といった、身近な“うっかり”の事例に触れることで、「あ、これは自分にもある」と気づけます。そこから行動が変わり始めます。本音で話ができる同僚同士で愚痴を吐き出しましょう。型ぐるしい研修だけでは解決策に近づけません。
完璧を目指さなくていい。「できる一歩」から始めよう
「すべてのルールを100%守れなければ意味がない」と考えると、行動へのハードルが高くなります。まずは、「今日だけは確認してから送信する」「この書類だけはWチェックする」など、小さな実践を積み重ねていくことが、習慣化への近道です。問題を口にしたらやってみることです。
人目を“味方”にする
「誰かに見られていたら、ちゃんとやる」――
そう感じるのは、あなたが責任感を持っている証拠です。
その心理を活かして、チーム内で声を掛け合う、行動が見えるようにするなど、“見られている仕組み”を味方にすると、自然と行動が変わります。
「たまたま」の積み重ねが、重大なリスクに
「今回はたまたま」…そう思っていた小さな油断が、今日に限って事故になることがあります。チェックリストやルールの明文化、リマインダー機能など、自分が忘れても同僚や仕組みが支えてくれる環境づくりを意識してみてください。
『人にしてもらいたいと思うことは、あなたも人にしなさい』
あなたが「やるべきと分かっている」からこそ、行動は変えられます。
完璧じゃなくていい、でも「意識して、少しずつ実行する」ことが、組織のセキュリティを支える大きな力になります。